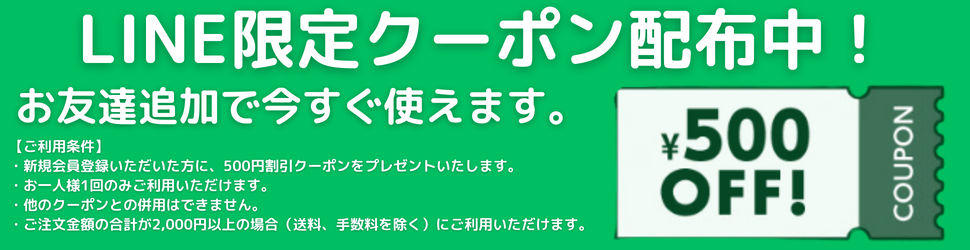ペットロスがつらすぎる……乗り越える方法は?ペットを失った人への接し方も

ペットとの毎日は、幸福と安らぎの連続です。
しかし命に限りがある以上、避けられないのがペットとの死別です。いつか訪れる別れを想像するだけで、胸を締め付けられます。
現在も、愛するペットとの別れによるペットロスに苦しんでいる人がいるでしょう。私も過去に愛犬に先立たれ、つらく悲しい日々を送った経験があります。
今回は、つらいペットロスを乗り越えるためのヒントをご紹介します。
大切な存在との死別の苦しみは、自分自身の力で乗り越えなくてはいけません。
本記事が少しでも心の支えになれれば幸いです。
ペットロスとは

ペットロスとは、愛するペットを失ったことによるネガティブな感情を指します。
また、ペットロスが原因で心身にさまざまな不調が引き起こされる状態を「ペットロス症候群」といいます。
動物を愛する人であれば、ペットロスに陥るのは自然なことです。心の支えだったペットを失うことによる精神的ダメージは筆舌に尽くしがたく、人によっては外出ができなくなってしまったり無気力状態になってしまったりすることも珍しくありません。
ペットロスに陥ったときに生まれる感情

否認
ペットロスに陥ると、さまざまなネガティブな感情に襲われます。
心理学的にまず湧き上がるとされているのが、否認の感情です。
「大切なペットを失ってしまったことを認めたくない」という気持ちが高まり、目の前の現実を受け入れることを拒否します。
現実逃避とも捉えられ、頭ではわかっていても自分の心を守るために事実を否定しようとします。
怒り
死は逃れられない現実だからこそ、他責にすることで一時的に悲しみから距離を置くことができます。
例えばペットを苦しめた病気や死因となった事故、果ては最善を尽くしてくれた獣医師やペット自身にまで怒りの感情が向くこともあります。
怒りの感情は、実際に相手を憎んでいなくても「自分の心を守るため」に芽生えます。
死別の苦しみを他の誰かや何かのせいにすることで、自らの心が背負わないように無意識にコントロールしているのです。
罪悪感
どんなにペットの死を他責にしようとも、現実が変わるわけではありません。
自分以外の対象に怒りの感情を抱くほど、最終的には「自分のせいだ」と己に返ってくるものです。
「もっと早く病気に気付いていれば助かったかもしれない」「安楽死を選んであげればよかった」「安楽死させたのは正解だったのか?」「もっと可愛がってあげればよかった……」など、自分を責めて追い詰めてしまいます。
抑うつ
ペットロスの主な症状である抑うつ状態は、無気力や元気の消失などが特徴です。ふとした瞬間にペットを思い出して悲しみが湧き上がり、後悔や不安感で塞ぎ込んでしまいます。
ペットロスによる抑うつ状態には個人差があり、数日程度で治まる人もいれば数ヵ月以上続いてしまう人もいます。ペットとの関係性はもちろん、飼い主さん自身の性格やペットの死因、今までの飼育環境や心理状態などによって変わるでしょう。
ペットロスの克服が困難な人の傾向

ペットを心のより所にしていた
私たちは生活の中でさまざまなストレスを受けますが、家族や生きがいなど何かしらの心のより所があることでメンタルをコントロールしやすくなります。
ペットを心のより所にしていた人は、死別によって「心を安定させる方法」も同時に失ってしまった状態です。
今まで悲しい出来事があったときにペットの存在に癒やしてもらっていた場合、心の傷を癒やす術すらもわからなくなってしまうのです。
ペット中心の生活をしていた
今までペット中心の生活をしていた人は、ペットがいなくなることで毎日の過ごし方がわからなくなってしまいます。
今までは人付き合いや仕事のシフトもペット中心で、それが当たり前だったはずです。
毎日の過ごし方における制限が突然なくなったことで、大きな喪失感を抱いてしまいます。
人間関係が希薄
心の傷を癒やすためには、悲しみや寂しさなどのネガティブな感情を誰かと共有するのが効果的とされています。
そのため、人間関係が希薄な人はペットロスを癒やしづらく、一人で苦しさを抱え込みやすいでしょう。
また自分に厳しい人は「人に弱音を吐くのはかっこ悪い」と自分を追い詰めてしまい、精神的に余裕がなくなることも珍しくありません。
趣味や物事への興味に乏しい
ペットを失った悲しみを癒やすためには、仕事や趣味など他の物事で気を紛らわせることも大切です。
しかし、元々趣味に乏しく物事への関心が薄い人は、悲しみを忘れる機会になかなか恵まれません。事あるごとに亡くなったペットを思い出し、気分転換ができないまま過ごしてしまいます。
後悔が残っている
「もっと遊んであげればよかった」「違う治療法を選択してあげればよかった」「忙しくてあまり構ってあげられない日も多かったな……」などのように、生前のペットとの生活に後悔がある人はペットロスから抜け出しづらいでしょう。
いくら後悔をしても時間は戻りません。「ああすればよかった、こうすればよかった」という気持ちだけが自分の中で膨らみ、罪悪感と寂しさがいつまでも拭えないものです。
ペットロスを乗り越えるために取り入れたい考え方

命は生まれたときから寿命が決まっている
ペットロスを乗り越えるためには、自分を否定しないことが大切です。そのためには新しい価値観を取り入れ、視野を広げてみましょう。
まず取り入れたい考え方が「命は生まれたときから寿命が決まっている」というものです。
哺乳類の心拍数は、生まれてから死ぬまでに打つ回数が同じであるといわれています。
飼育環境次第で後天的に寿命を延ばすことは可能ですが、そもそも人間がペットにしてあげられることは限られています。
幸福のためには、いかに長く生きるのかではなく、決められた命をどう過ごすかのほうが大切です。これは、人間でもペットでも変わりません。
悲しみを否定する必要はない
ペットロスを克服するためには、悲しみの感情を受け入れる必要があります。
自分の中にネガティブな感情が生まれたときに最もしてはいけないのは、自分の感情自体を否定することです。
悲しい気持ちは、悲しいままで構いません。「私は悲しくない」「寂しがっていては駄目だ」と自分を追い詰める必要はないのです。
愛しいペットがいなくなってしまった事実は、紛れもなく悲しいことです。存分に悲しむことで、次への一歩を踏み出せるでしょう。
もちろん、無理に悲しむ必要もありません。自分の中に自然と沸き上がった感情を、あるがままに受け入れることが大切です。
新しいペットを迎えることは罪ではない
ペットロスに苦しむ人の中には、新しいペットを迎え入れることを検討している人もいるでしょう。
しかし「前の子のことを忘れてしまうかもしれない」「死んでしまった子が悲しむだろうか……」と悩み、なかなか決断できない人も多いのではないでしょうか?
新しいペットを受け入れること自体は、決して悪いことではありません。
亡くなってしまった子と新しい子とは、別の命です。新しい思い出が増えることはあっても、昔の思い出がなくなることはありません。心のアルバムに上書きされるのではなく、新しいアルバムがもう一つできると考えましょう。
ペットロスを乗り越えるためのヒント

やるべきことをやり、時間の経過に身を委ねる
ペットロスを乗り越えるためには、自分の日常に意識を向けましょう。
安心してください、あなたが日常を生きても亡くなった子の記憶がなくなることはありません。注いだ愛情の分だけ、あなたの中にしっかりと生き続けます。
苦しみの渦中にいると「つらい気持ちは時間が解決してくれる」という言葉は安っぽく感じるかもしれません。しかし今までの人生でも、心の痛みを時間が和らげてくれたことはないでしょうか?
ペットを失った事実は消えませんが、時間が心を癒やしてくれるケースは多いものです。
悲しみと向き合いすぎて心を壊してしまう前に、まずは仕事や家事など「日々のやるべきこと」に尽力しながら、時間に身を任せてみましょう。
悲しみを一人で抱えず誰かと共有する
ネガティブな感情は、一人で抱えているとどんどん肥大してしまうものです。
悲しみが心のキャパシティを超えてしまう前に、気持ちを言葉にして誰かと共有しましょう。
家族や友人、恋人など身近な相手でも構いませんし、SNSに投稿するのもよいでしょう。同じようにペットロスの傷を抱える人たちが集まる掲示板に書き込むのもおすすめです。
大切なのは「気持ちを外に出すこと」です。
喜びは分かち合い、悲しみは分け合う。自分以外の人とのコミュニケーションは孤独を癒やし、前向きな心を取り戻すためのきっかけになります。
身近な人がペットロスに……どう接すればよい?

価値観を押し付けず、相手の気持ちに寄り添おう
ペットロスで苦しんでいる人を見ると、どのように声をかければよいのか困惑してしまいますよね。
心がけたいポイントは、自分の価値観を押し付けないことです。
飼い主さんは、まさに悲しみの真っただ中にいます。まずはその悲しみに寄り添い、「つらいよね」「悲しいよね」「こんなに悲しんでもらえるなんて、〇〇ちゃんは幸せ者だね」のように、共感することをおすすめします。
精神的に回復するためのアドバイスを与えるときも、押し付けや無理強いがないように注意しましょう。
お悔みの贈り物
お悔みの贈り物を選ぶ際は、亡くなった子が好きだったおやつや普段食べていたフードが喜ばれます。また新品のおもちゃや、写真立てもよいでしょう。
ペット用の仏壇を所持している人には、ペット専用の仏具のギフトもよいですね。
お花やお供え用のクッキーなどを贈ることでも、お悔みの気持ちを伝えられるでしょう。
ペットロスの人に言ってはいけない言葉
ペットロスでつらい思いをしている人には「自分の価値観を押し付ける言葉」と「相手の感情を踏みにじる言葉」は使わないように心がけてください。自分にはそのつもりはなくても、心が敏感になっている相手には違った意図で伝わってしまう場合もあります。
例えば「早く元気出しなよ、仕事も忙しいんでしょ?」や「いつまでもクヨクヨしたら駄目だよ」などの言葉は、よかれと思って言ったつもりでも相手を傷付けることがあります。
間違っても「新しい子を飼えば?」や「たかがペットでしょ?」と言ってはいけません。
まとめ

今回は、ペットロスを乗り越えるためのヒントをご紹介しました。
ペットロスはペットを飼っているすべての人が必ずと言ってよいほど抱く感情ですが、死生観やペットとの付き合い方によって症状や期間は変わります。
大切なのは、自分自身の感情を否定せずに受け入れること、そしてペットとの優しい記憶はそのままに、意識を外側に向けることです。
自分のペースを最大限に尊重しながら、少しずつ新しい明日に向かって歩み出しましょう。