【ペットショップ店員が解説】うさぎのくしゃみの原因と対処法、今後の予防方法について解説!
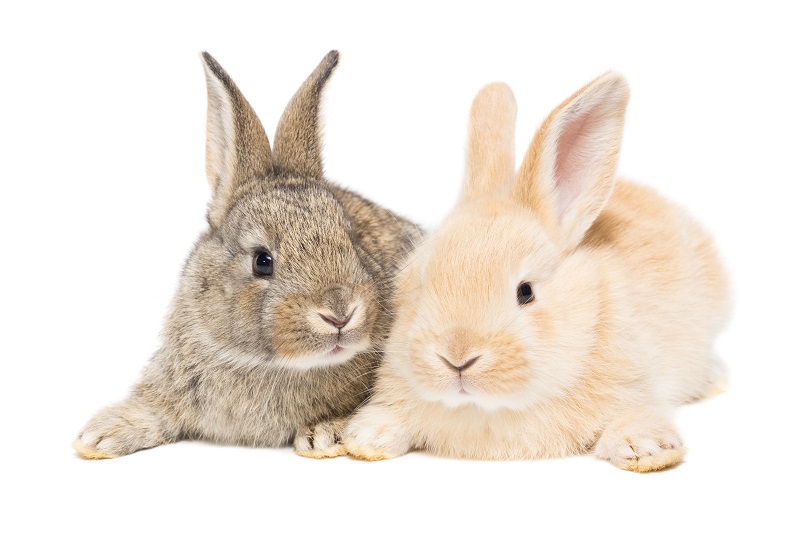
みなさんの飼っているうさぎは、くしゃみに悩まされたことはありませんか?
うさぎは体が小さいだけに、全身を震わせてくしゃみをします。
そんな姿をみたら、とても心配になりますよね。
今回は、うさぎのくしゃみについて、原因と対処法、そして今後の予防方法についてご紹介していきます。
みなさんの飼っているうさぎの仕草や、飼育環境と照らし合わせながら確認してみてくださいね。
うさぎのくしゃみに悩んだことがない方も、予防方法が載っているので参考にしてみてください。
うさぎのくしゃみの原因は?

不正咬合
うさぎのくしゃみの原因は、不正咬合であることが多いです。
不正咬合とは、上下の歯がうまく嚙み合わない状態のことを指します。
うさぎは一生歯が伸び続ける動物なので、草やかじり木を嚙むことで歯をすり減らします。
しかし、それが何らかの原因でできなくなり歯が適切な長さに保てなくなると、不正咬合になってしまいます。
不正咬合はくしゃみ以外にも口腔内の怪我や食欲不振を引き起こしてしまうので、絶対に避けたい状態です。
お部屋がほこりっぽいのかも

うさぎは部屋のほこりや牧草の粉を吸い込むことで、くしゃみをすることがあります。
そのくしゃみがすぐにおさまるものであれば、大きな心配はありません。
しかし、常にくしゃみをしている状態であればそもそもの飼育環境を見直す必要があるでしょう。
掃除機ではなく水拭きをするようにしたり、空気清浄機を使ってみるのも一つの手です。
また、チモシーやアルファルファなどの牧草を与える際には、粉をふるってから与えるようにすると、改善されることがあります。
「細菌」に感染している

うさぎは、細菌によってくしゃみが出ることがあります。
ここでは、その細菌の中でよくみられる2つの菌についてご紹介します。
また、細菌によってくしゃみや鼻水が出る状態のことを、まとめてスナッフルと呼びます。
うさぎ梅毒
うさぎのくしゃみの原因の細菌に、うさぎ梅毒というものがあります。
感染経路としては以下のようなものがあります。
・うさぎ梅毒に感染したうさぎとの交尾や粘膜接触
・うさぎ梅毒にかかった親からの授乳
感染しても、症状がでない状態のうさぎが多いと言われます。
くしゃみの他に、鼻にかさぶたができたり、生殖器に水膨れができたりといった症状があります。
これらの症状と合わせて確認し、安易にスナッフルと判断しないようにしましょう。
パスツレラ菌
うさぎの呼吸器系の病気の多くは、パスツレラ菌によるものとされています。
パスツレラ菌は、うさぎだけでなく、多くの犬や猫、鳥に潜む細菌です。
この菌に感染し体調が悪化すると、呼吸器系の疾患が現れ、その症状の一つとしてくしゃみを引き起こします。
この菌は常在菌なので、感染を防ぐことはできず、また感染したからといってすぐに症状が出るわけではありません。
また、パスツレラ菌は常在菌なので、一度完治しても再発する可能性があります。
免疫力を高め、感染しても発症しないようにすることが大切です。
うさぎにもアレルギーがある

うさぎにも、人間と同じようにアレルギーがあります。
もともと野生のうさぎがペットとして飼われるようになり、周りに存在する菌が偏ったことでアレルギーを発症することが知られてきました。
そのアレルギーは、菌だけでなく、食べ物やトイレ砂、木材に対しても発症することがわかっています。
アレルギーが考えられる場合は、動物病院に受診し、アレルギーの検査をすることをおすすめします。
与えている食べ物や、つかっているかじり木などを変えるだけで、状況が大きく改善する可能性があります。
うさぎの高齢化
高齢のうさぎは、くしゃみをすることが多いです。
高齢そのものが理由というよりは、高齢が原因で免疫力が低下し、ちょっとした体調不良が症状に出てしまいやすくなるということが理由です。
若いころには考えられなかった些細な理由でくしゃみをするようになっているので、もう一度心当たりを細かく探ってみてください。
うさぎのくしゃみへの対処方法
まずは病院へ

うさぎのくしゃみは、不正咬合やアレルギー、感染症が原因となっていることが多く、その場合飼い主さん自身で簡単に治すことができません。
症状の進行がすすまないうちに動物病院を受診し、原因を突き止めてもらいましょう。
原因が細菌だった場合、抗菌薬の投与が行われます。処方された薬は、最後まで飲み切るようにしましょう。
うさぎが薬を嫌がって飲まない時は、ペースト状のおやつに混ぜ込むのがおすすめです。
ペットショップ店員の私のおすすめは、イースター社の『セレクションプロプラス バイタルチャージ』です!
これをお湯で溶いてペースト状やお団子状にすると、お薬が混ぜ込まれていても喜んで食べてくれる子が多いです。
温度管理を適切に

部屋の温度を適切に保ってあげるようにしましょう。
特に季節の変わり目や夏の高温多湿は、うさぎの免疫力を低下させてしまいます。
エアコンを上手に使い、
・温度を24~26℃
・湿度を50%前後
に保ってあげましょう。
冬は、ヒーターを使って保温することが大切です。
「昔小学校で外でうさぎを飼っていたし、冬でも大丈夫!」と思われるかもしれませんが、屋外で飼われているうさぎは、穴を掘って寒さをしのいでいます。
屋内で、ペット用として飼われているうさぎは、自分で保温することができません。
遠赤外線タイプの電球ヒーターと、自分で乗って温まるボードタイプのヒーターを併用し、ケージ内を暖かく保つようにしてあげましょう。
お部屋の空気を清潔に
部屋にほこりや牧草の粉が飛び散らないように、清潔に保ちましょう。
ケージやおもちゃはこまめに掃除・消毒し、室温を一定に保ちながら換気を行いましょう。
また、うさぎが細菌に感染していた場合、くしゃみによって菌が飛び散り他の動物に感染させてしまいます。
特にパスツレラ菌はうさぎだけでなく動物にとって共通感染症なので、多頭飼育の方は注意するようにしましょう。
うさぎのくしゃみへの予防方法
うさぎの免疫力を高める

うさぎのくしゃみを予防するには、免疫を高めることが大切です。
免疫を高めることで、うさぎがもともと持っている細菌や、新しく感染してしまった細菌を抑え込むことができます。
免疫を高めるためには、食事、運動、ストレスのない生活を整えることが大切です。
食事については、牧草とペレットフードをバランスよく食べていることを確認しましょう。
また、おやつをあげている場合には、おやつによって摂取している栄養が偏らないようにしましょう。
運動については、毎日適度に体を動かしていることを確認しましょう。
一日数時間はケージの外に出してあげて、部屋んぽ(お部屋の中でお散歩したり、遊ぶこと)をさせてあげるようにしましょう。
ストレス軽減のためには、飼い主さんがしっかりコミュニケーションをとってあげることが大切です。
うさぎは、あまり懐かないイメージとされていますが、そんなことはまったくありません。
飼い主さんのことを大好きで、構われないと寂しさを感じます。
そのため、一緒に遊んであげる時間やスキンシップの時間を十分に確保するようにしましょう。
しっかり牧草を食べてもらう
くしゃみを予防するために、牧草をしっかり食べてもらうようにしましょう。
特に、繊維質が多いチモシーの一番刈りがおすすめです。
繊維質の牧草を食べることで、くしゃみの原因となる不正咬合を予防することができます。
さらに、不正咬合の予防だけではなく、お腹の調子も整えてくれるという効果があります。
お部屋を清潔に
部屋は常に清潔に保つようにしましょう。
異物が鼻やのどに入ってしまって引き起こすくしゃみや、アレルギーによるくしゃみを予防することができます。
部屋を清潔にすることは、くしゃみの予防だけではなく皮膚病の予防にも繋がります。
ケージや牧草いれ、餌皿は定期的に清掃・消毒を心掛けましょう。
小動物用の消毒スプレーを効果的に使うと、清潔な環境を保ちやすくなりますよ。
まとめ

いかがでしたか?うさぎは、野生では捕食される動物なので、体調の悪さを隠そうとする習性があります。
うさぎの体調のわずかな変化に気づいてあげられるのは、飼い主さんだけです。
くしゃみやその他の体調のサインを見逃さないように、毎日コミュニケーションをとってあげてくださいね。



