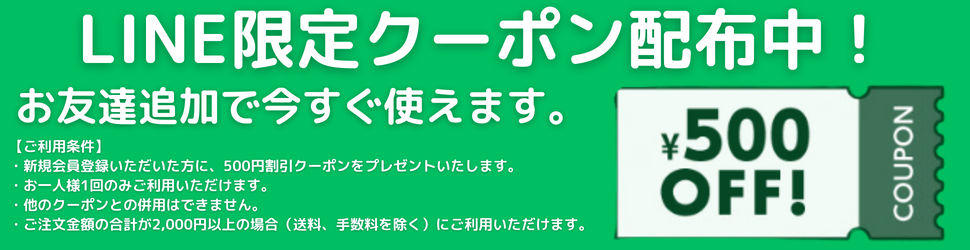【犬・猫】マイクロチップの装着が義務化?機能やメリット、気になる費用も解説

「マイクロチップの装着」は、犬や猫の迷子対策の一つとして推奨されています。
とはいえ、体に異物を埋め込むことへの抵抗がある人も多く、実際に装着している犬や猫は多くないのが現状です。
マイクロチップの装着は、日本政府により動物愛護管理法が改正され、2022年6月から義務化されることが決定しました。
義務化されることで、「痛そう」「副作用があるのでは」とデメリットが気になっている方も多いのではないでしょうか?
マイクロチップとはどのようなものなのか、すでに飼われている犬や猫も義務づけられるのかなど、詳しく解説します。
マイクロチップとは?

マイクロチップとは、カプセルに包まれた電子標識器具です。
カプセルの大きさは直径1~2mm、長さ8~12mmととても小さく、小型の集積回路とコイルアンテナが入っています。
15桁の個体識別番号が記録されており、リーダーで読み取ることで飼い主がわかるという仕組みです。
難しく聞こえますが、デジタルな迷子札と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
マイクロチップに登録される内容は?
マイクロチップには、飼い主の情報とペットの情報の両方が登録されます。以下の内容を飼い主の情報として登録しましょう。
■飼い主の情報■
・名前
・住所
・電話番号・FAX番号・その他の緊急連絡先のいずれか1つ以上
・Eメールアドレス
登録するペットの情報は、以下の通りです。
■ペットの情報■
・名前
・生年月
・性別(オス・去勢オス・メス・避妊メス・不明)
・動物の種類
・犬・猫の種類
・毛色
その他、獣医師の氏名や動物病院名なども登録されます。
GPS機能はない
マイクロチップには、居場所がわかるGPS機能は付いていません。
迷子になった犬や猫から飼い主の連絡先を知ることはできますが、飼い主側からは見つけ出すための手がかりにはならないということです。
ペットの行方がわからなくなったときは、マイクロチップを読み取ってもらって連絡が来るのを待つしかありません。待つことしかできないのはつらいですが、誰かが保護してくれれば戻ってくる可能性は高いです。
位置情報を確認できるようにするには、GPS機能付きの首輪を装着するなどマイクロチップ以外の対策が必要になります。
マイクロチップの寿命は?
マイクロチップの寿命は30年前後です。犬や猫なら途中で交換することもなく、生涯安心して使えます。
念のため、定期的にマイクロチップが正常に作動するかどうかを確認してもらうと安心です。健康診断や通院のときに、ついでにチェックしてもらいましょう。
マイクロチップ装着は増えている
欧米を始め、多くの諸外国でマイクロチップの装着が義務化されています。
ペットを連れて海外へ行く際の検疫でもマイクロチップが確認されるため、一般的になりつつあるといえるでしょう。
日本でも2011年の東日本大震災で迷子になった犬や猫が多かったことから、マイクロチップを装着させる人は増えているといいます。
2022年6月からマイクロチップが義務化

マイクロチップが義務化されるのは、2022年6月からです。
義務化によって何が変わるのか、どのくらいの費用がかかるのかなどを解説します。
これから犬や猫を飼う予定の人も、すでに飼っている人もチェックしておいてくださいね。
義務化の対象は?
マイクロチップの装着が義務づけられるのは、ペットショップやブリーダーで販売される犬や猫が対象です。
つまり、犬や猫を飼いたい人がペットショップやブリーダーのもとを訪れるときには、すでに装着が済んでいることになります。
飼い主はペットを購入後、マイクロチップに登録されている内容を変更するだけでOKです。
登録の費用は?
マイクロチップの情報を登録するときも内容を変更するときも、手数料がかかります。
パソコンやスマートフォンによるオンライン申請なら1回につき300円、紙での申請なら1回につき1,000円です。
今飼っている犬や猫も義務?
義務化される前に飼い始めた犬や猫については、マイクロチップの装着は「努力義務」とされています。
つまり、「義務ではないけれど装着するよう努めてほしい」ということです。
保護犬・保護猫団体から譲り受ける場合も、同様です。
のちほどお伝えするメリット・デメリットをチェックして、マイクロチップの装着を検討してみてくださいね。
マイクロチップの装着方法

マイクロチップは、獣医師が器具を使って皮膚の下に埋め込んでくれます。
首のうしろに埋め込むのが一般的です。
犬は生後2週間くらいから、猫は生後1ヶ月くらいからの装着が推奨されています。
痛みは?
マイクロチップの埋め込みに使われるのは、注射器よりも先が太くなっている埋め込み器です。
もちろん痛みはありますが、一瞬で済むため麻酔を使わないケースが多いでしょう。
去勢・避妊手術など麻酔を使うタイミングで埋め込んでもらうことも可能です。
飼い主の希望に応じて麻酔や鎮静剤を使ってくれる場合もあるため、獣医師に相談してみてくださいね。
触るとわかる?
マイクロチップを埋め込んだ場所を触ると、カプセルの感触がわかることがあります。
多少の衝撃を受けてもマイクロチップは壊れませんが、移動してしまう可能性はあるため注意しましょう。
体内を移動しても健康に影響はありませんが、読み取るときにマイクロチップの場所がわからなくなり不便です。あまり触らないように心がけてくださいね。
マイクロチップは安全?副作用は?
マイクロチップには体内に入れても問題のない素材が使われているため、安全です。
いくつもの臨床試験をクリアしているため、安心してくださいね。
アナフィラキシーショックなどの副作用も、ほとんど報告されていません。
日本においては、これまでに1件もないといわれています。
値段や装着にかかる費用は?
マイクロチップ自体の値段や装着にかかる費用は、動物病院によって違います。
処置に必要な費用は、トータルでおよそ4,000~10,000円程度です。麻酔を使う場合は、さらに麻酔料金がプラスされます。
助成金制度がある市区町村もあるので、ぜひ問い合わせしてみてくださいね。
マイクロチップを装着するメリット

マイクロチップ装着の義務化は、犬や猫の「迷子」や「無責任な遺棄」を減らすことが目的です。
多くの飼い主はペットを家族として大切にしているため、「迷子にさせないし捨てることもない」と考えていることでしょう。
その上でマイクロチップを装着するメリットをお伝えします。
迷子になったときに戻ってくる可能性が高い
マイクロチップを埋め込む最大のメリットは、迷子になったときに保護されれば連絡がくるということです。
対策をとっていても、迷子になる可能性はゼロではありません。
というのも、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震で、飼い主とペットが離ればなれになってしまうケースが多発したからです。
保護された犬や猫の多くにマイクロチップが装着されておらず、飼い主のもとへ帰れませんでした。
思わぬ事態で迷子になる可能性を考えると、マイクロチップの装着は重要だといえます。
首輪が外れても|首輪を嫌がる猫にも
「飼い主の連絡先を書いた首輪をしているから大丈夫」と考える人も多いかもしれません。
ですが、首輪は外れてしまったり、汚れて連絡先が読み取れなくなってしまったりする可能性があります。
マイクロチップなら、体から抜けることはありません。首輪を嫌がる猫にも有効です。
盗難対策になる
コンビニやスーパーに入る際、入口にリードを結んで犬を待たせている間に盗難に遭った。また、窓を開けた車の中で待たせている間に犬を連れ去られたというケースもあります。
マイクロチップが普及すると「調べれば本当の飼い主がわかる」という考え方が一般的になり、盗難自体が減るはずです。そのためにも、すでに飼っている人もマイクロチップの装着を検討してみてくださいね。
マイクロチップを装着するデメリット

マイクロチップを埋め込むのは簡単ですが、取り出すときは手術が必要になります。
実際に装着する前に、マイクロチップのデメリットもチェックしておきましょう。
マイクロチップを正しく理解した上で装着させてあげてくださいね。
埋め込み時に痛みが伴う
マイクロチップを埋め込むときは、注射と同じくらい、あるいは注射よりやや強めの痛みを感じるといいます。
「病気の治療や予防でもないのに痛みを与えるのはかわいそう」と感じる人も多いのではないでしょうか。
嫌がるのを押さえつけられている姿は、できれば見たくないですよね。麻酔や鎮静剤を使ってくれる場合もあるため、獣医師に相談してみましょう。
読み取るにはマイクロチップリーダーが必要
マイクロチップの個体識別番号を読み取るには、専用のリーダーが必要です。
動物病院にはあっても、すべての保健所や保護犬・保護猫団体に置いてあるわけではありません。
迷子の犬や猫が保護されても、飼い主が見つかるまでは時間がかかる可能性があります。
マイクロチップの義務化に合わせ、リーダーを置く施設が増えることを期待しましょう。
引っ越しの度に届け出が必要
マイクロチップには、住所や電話番号を登録します。
引っ越しの度に変更届を出さなければならず、手続きを忘れてしまうと迷子になってもペットは戻ってこられません。
飼い主が変わった場合や亡くなった場合も、届け出が必要です。変更が多い人にとっては、手間と感じるかもしれませんね。
まとめ

マイクロチップは、思いがけない事態が起きたときにペットを守ってくれます。
埋め込み時に痛みはありますが、健康を害する心配はありません。
大切なペットと離ればなれにならないように、マイクロチップが活躍してくれるでしょう。