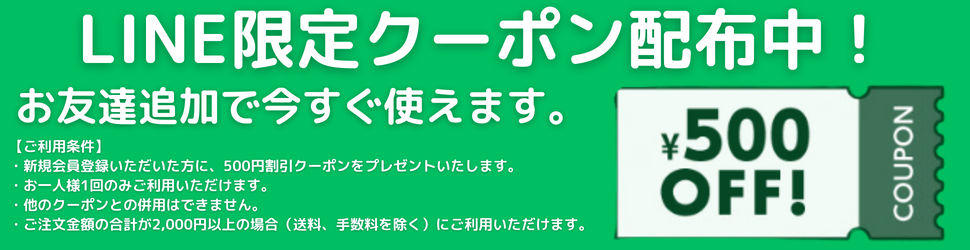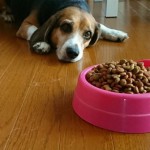愛犬の夏バテ・熱中症防止にぴったり?犬にきゅうりを与えるメリットや注意点

夏野菜の代名詞の一つでもある、きゅうり。
サラダやぬか漬け、ピクルスなどさまざまな調理法で私たちを楽しませてくれますが、生のきゅうりは犬にとってもメリットがあります。
今回は、犬にきゅうりを与えるときのポイントや注意点などをご紹介します。
適切に与える方法を学び、犬と一緒に安全で楽しい食生活を楽しみましょう。
きゅうりは「最もカロリーの低い果実」としてギネスに認定済!

私たちの食生活において身近なきゅうりですが、実は「最もカロリーの低い果実」としてギネスブックに認定されていることはご存じでしょうか?
和訳の過程で「最も栄養価が少ない果実」として伝わっているケースがありますが、これは原文である「Least calorific fruit」を読めばわかるように間違いです。
きゅうりには数々の栄養素があり、犬も人間と同じように食べられます。
そしてきゅうりは犬にとっても、さまざまなメリットがあるのです。
犬にきゅうりを与えるメリット

水分たっぷりで夏バテ・熱中症防止に適している
きゅうりは、数ある野菜や果実の中でもトップ3に入る水分量を含んだ食材です。なんと全体の95%が水分で構成されているというのですから驚きです。
水分補給をしつつ体を内側から冷やしてくれるため、夏バテや熱中症を防止してくれます。
普段あまり水を飲んでくれない子も、きゅうりのシャクシャクとした食感はおやつとして好んで食べてくれることがあります。
他の野菜と比較してカロリーや脂質も低く、ダイエットのサポート食品としても活躍してくれるでしょう。
また、夏場だけではなく、空気が乾燥した冬場にも容易に水分摂取ができます。
カリウムで血圧を下げる
きゅうりには多くのカリウムが含まれています。
カリウムはミネラルの一種で、体の中にたまっている塩分を排出し、血圧を下げる作用があります。神経や細胞が正常に働くようにサポートしてくれる成分です。
ビタミンKで骨を丈夫に
ビタミンKの主な役割は、止血作用と骨を丈夫にすることです。
出血をしたときにしっかりと血液が止まるよう、凝固作用に好影響を及ぼしてくれます。骨が丈夫になるようにカルシウムを定着させてくれるのもビタミンKです。
犬は自分の体の中でビタミンKを生成できないため、総合栄養食やきゅうりのような食材から取り入れる必要があります。
ホスホリパーゼで脂肪を分解
普段はあまり聞き馴染みがない栄養素であるホスホリパーゼですが、脂肪分を分解するという嬉しい役割を持っています。
特にきゅうりに含まれているホスホリパーゼは分解力が高く、ダイエットや肥満防止にはぴったりだといえるでしょう。
βカロテンで老化防止・健康維持
βカロテンは抗酸化作用を持つ成分で、老化や関節炎の予防などの効果が見込めます。
犬の体内に入ることでビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の健康維持にも役立ってくれるでしょう。
さらに、暗闇での視力をサポートする効果もあります。
犬にきゅうりを与えるときの注意点

与えすぎると水分過多で下痢の原因になる
きゅうりは水分補給におすすめの食材ですが、与えすぎると水分過多となり体を冷やしすぎてしまい、下痢の原因となります。
きゅうりの1日あたりの目安摂取量をまとめましたので、参考にしてくださいね。
・小型犬(5kg程度まで):145g~288g
・中型犬(6~15kg程度):330g~657g
・大型犬(20kg程度~):815g~1620g
(*平均的なきゅうり1本の重さは約104g)
上記を目安に、年齢や健康状態によって量をコントロールしながら適量を与えましょう。
栄養の総量が少ないため主食にはしない
きゅうりには多くの栄養素が含まれていますが、栄養の総量は多くありません。
そのため主食としては活用せず、おやつの代わりとして与えるよう心がけてください。
喉に詰まらせないように小さく切る
小型犬に限らず、きゅうりをそのまま与えると喉に詰まらせてしまう可能性があります。
SNSなどできゅうりを丸ごと一本与えている画像を見かけますが、安全性の観点から見ると控えるべきといえるでしょう。
丸飲みしても危険がないように、2~3cmを目途に普段与えているおやつ程度の小ささまでカットして与えてください。
皮は剥いてから与える
きゅうり自体は消化に悪い食べ物ではありませんが、皮の部分は固いため消化の弊害となります。与えるときは皮を包丁やピーラーで剥いてあげてから、実の部分のみを与えるように心がけましょう。
とくに消化器官が弱っているシニア犬や、成長過程の子犬に与える場合は気を付けてくださいね。
腎臓が弱っている犬には与えない
きゅうりに含まれているカリウムは健康な体づくりをサポートしてくれますが、腎臓の機能が低下している犬には危険な成分となります。
腎機能が弱っていると、多量のカリウムを摂取することで高カリウム症という病気を患ってしまう危険性があります。
不安な飼い主さんは、事前に動物病院で検査を受けさせましょう。
きゅうりの加工品はNG

犬にきゅうりを与えるときは、基本的には生のままで与えてください。ドレッシングやマヨネーズをかけたもの、ぬか漬けやピクルスに加工したものを与えるのは厳禁です。
塩分が多く含まれているため、体を壊してしまう可能性があります。
とくにドレッシングには犬にとって命に関わる危険な食材であるたまねぎが含まれている可能性があり、危険です。
酢のみで味付けされたきゅうりは問題ないともいわれていますが、犬は嗅覚が鋭く人間が気にならない酢の匂いにも敏感に反応します。
生のままで問題がないものを、味をや匂いを付けた状態で与える必要はないでしょう。
最初は少量ずつ与えて様子を見る
人間と同じように、犬もきゅうりでアレルギーを発症する可能性があります。
アレルギーの症状は、かゆみや嘔吐、下痢などが代表的です。
最初に与えるときは少量ずつにして、体調に変化がないことを確認した後に日数をかけて量を増やしていきましょう。
きゅうりはウリ科の植物であるため、以前にスイカ・メロン・ゴーヤ・ズッキーニなどでアレルギー反応が出た犬には与えないようにしてください。
また、人参や花粉のブタクサにアレルギーを持つ子の場合、体が抗原だと勘違いしてアレルギー症状が出る交差反応を起こす可能性があるため、とくに注意を払ってください。
普段から総合栄養食を食べている子は、きゅうりを食べなくても十分な栄養を摂取できています。きゅうりにあまり口を付けなかったり吐いたりした場合は無理に与える必要はありません。
ヘタは取りのぞく
稀に感じるきゅうりの苦みはククルビタシンという成分が含まれているためですが、ククルビタシンは人間にとって有毒であり、大量に摂取すると食中毒を引き起こします。
また、ククルビタシンは実の部分よりもヘタに多いとされています。
人間と同様に犬にも危険である可能性が高いため、ヘタは必ず取り除いてから与えるようにしてくださいね。
実にクルビタシンが多く含まれているきゅうりは、人間が食べても苦みを感じます。犬に与える前に味見しておくと安心でしょう。
特に注意!食べすぎによる高カリウム血症の症状とサイン

犬にきゅうりを与える際に気を付けるべき点が、カリウムの多量摂取です。
とはいえ、愛犬の体内にカリウムがどの程度蓄積されているかを目で見ることはできません。
カリウムの多量摂取により発症リスクが上がる高カリウム血症の症状を記載しますので、犬の様子を観察しながら違和感やサインにすぐ気付けるようにしておきましょう。
・四肢のしびれ
・筋肉の衰え
・痙攣
・不整脈・頻脈
これらの症状が起こったら要注意です。
高カリウム血症は、最悪の場合は突然死してしまう可能性もあります。少しでも異常を感じたら、自己判断せずにすぐに動物病院を受診しましょう。
とくに下痢や嘔吐を繰り返すと、体の水分がどんどん外に出て脱水状態になってしまう危険があります。
いざというときに慌てないように、目立つ場所に最寄りの動物病院の住所や電話番号を控えておきましょう。
とくにシニア犬は普段から定期的に検査を行い、腎臓の異変にできる限り早く気付けるよう心がけてくださいね。
犬にきゅうりを与えるときの活用方法

普段のフードにトッピングする
犬にきゅうりを与えるときは、普段のフードにトッピングする形で添えてあげましょう。
薄くスライスしてサラダのように添えてもよいですし、細かくみじん切りにしてふりかけのように上からかけてもよいでしょう。
もちろん、きゅうり単体を間食として与えても構いません。
ダイエット中のごはんのかさ増しにする
ダイエットの必要がある犬に与えるときは、フードに混ぜてごはんのかさ増しをするのもおすすめです。
今まで必要量よりも多いごはんを食べて太ってしまった子は、通常量であってもダイエット期間の食事量に不満やストレスを感じる場合があります。
きゅうりでかさ増しすることにより食事の満足感が上がり、ストレスも減るでしょう。
水に1時間程度さらすと安心
カリウムの多量摂取が不安な飼い主さんは、きゅうりを与える前に水に晒したり煮たりするとよいでしょう。
カリウム自体は水溶性の成分のため、30分~1時間程度水に濡らすと溶けます。
反対に、カリウムをしっかりと与えたい場合は、さっと水で洗う程度に留めておきましょう。
まとめ

今回は、犬にきゅうりを与えるメリットや注意点などをご紹介しました。
きゅうりは水分を多く含んでいるだけでなく、ローカロリーで栄養補給ができる食べ物です。
とくに夏はスーパーの店頭にも並びやすく、人間にとっても犬にとっても美味しく食べられる時期でしょう。
与え方や注意点を正しく理解し、安全で楽しい食事の時間を過ごしてくださいね。